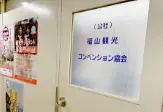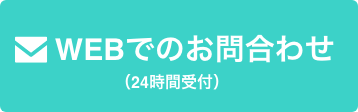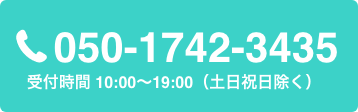Before Introduction
3市をまたぐ広域イベントに最適!費用対効果が高く参加者の利便性を最大化するシステムを導入!
導入前の課題や背景
デジタルスタンプラリーの導入を検討したきっかけは何ですか?
システム導入前に抱えていた具体的な課題や問題点を教えてください。
私たちがデジタルスタンプラリーの導入を検討することになったきっかけは、新型コロナウイルスです。「せとうち旅情」実行委員会は、瀬戸内地区の豊富な観光資源をPRし、観光イメージの高揚をはかり、3市(福山市・尾道市・倉敷市)とJR西日本が協働して、3市及び瀬戸内地区の活性化と観光客の誘致拡大を目的としている任意団体です。
新型コロナウイルスが流行し始めてから、密を避け、不要不急の外出を控えるようになり、人の移動が制限されていました。その一方で、密を避けながら楽しめる交通手段としてサイクリングに注目が集まるようになりました。そこで、サイクリングを取り入れた3市を周遊するスタンプラリーを実施しようという話が持ち上がりました。
しかし、紙のスタンプラリーを採用するとなると、サイクリング中に紙を携帯する煩わしさや、汗や雨によってスタンプが滲んでしまう問題が懸念されました。また、チェックポイントを設置する各施設にスタンプ台を設置する必要があり、管理の手間や紛失のリスクも考しなければなりません。さらに、参加者の利便性を考えたとき、スマートフォン一つで完結できるデジタルの方が適しているのではないかという結論に至りました。
このような背景から、デジタルスタンプラリーの導入を検討し始めました。特に、スマートフォンのGPS機能を活用することで、チェックポイントでの認証がスムーズに行える点や、スタンプの滲みや持ち運びのストレスがない点が大きなメリットでした。また、イベントの運営側にとっても、デジタルならリアルタイムで参加状況を把握でき、データ分析が可能になることも導入の後押しとなりました。
選定理由
他社のシステムと比較して、特に魅力を感じた点は何ですか?
数あるシステムの中から、なぜfurariを選ばれたのか、その決め手を教えてください。
デジタルスタンプラリーの導入を決めた後、数あるシステムの中から最適なものを選定する必要がありました。特に、予算の制約がある中で、コストと機能のバランスが取れたシステムを探していました。
最初は、オリジナルのアプリを開発する案も検討しましたが、見積もりを取ったところ、開発費が高額になり、これだけで予算の大部分を消費してしまうことが判明しました。そのため、既存のサービスの中から適したものを選ぶ方針に変更しました。
furariを選んだ決め手は、まずコスト面の優位性でした。潤沢な予算がないなかで、低コストで導入・運営できる点は非常に魅力的でした。また、ブラウザベースのシステムではなく、アプリ型であることも選定理由の一つでした。自転車利用者は40代から60代の方が多く見られ、アプリのダウンロードに抵抗を感じる方もいる一方で、20代から40代の参加者にはアプリの利便性が好評でした。こうした年齢層の違いも考慮しながら、最も適した形で導入できるシステムを求めていました。
また、furariの管理画面がシンプルで使いやすかったこともポイントでした。イベント運営側がスタンプポイントの設定や情報管理をスムーズに行えることは、実際の運用において重要な要素です。特に、チェックポイントの管理やデータの取得がしやすい点は、運営の負担を軽減できると判断し、最もコストパフォーマンスが高く、運営しやすいfurariの導入を決定しました。

導入プロセス
導入プロセスで予想外の困難や障害はありましたか?
導入にあたり、準備や設定で苦労された点があれば教えてください。
デジタルスタンプラリーの導入が決まり、実際の準備や設定を進める中で、いくつかの課題に直面しました。特に苦労したのは、チェックポイントの位置情報の設定でした。3市それぞれの担当者が施設の緯度経度データを提供し、それを基にチェックポイントを登録する必要がありましたが、実際にスタンプを取得できる範囲の調が難しい部分でした。
例えば、ある施設内に複数のQRコードを設置した際に、一部の場所では正常にスタンプが取得できるのに、他の場所では反応しないという問題が発生しました。こうしたトラブルを防ぐために、範囲の再設定やテストを繰り返す必要がありました。
また、イベント開始後にも「チェックポイントでスタンプが取得できない」といった問い合わせが寄せられることがあり、リアルタイムでの対応が求められる場面もありました。範囲を広げることで解決できるケースもありましたが、細かい調整が必要であり、また、参加者の回線による問題もあり、試行錯誤を重ねながらの運用となりました。
一方で、furariの管理画面はシンプルで直感的に操作できたため、基本的な設定作業に関しては大きな問題はありませんでした。スタンプポイントの追加やデータ管理が容易であったことは、運営側にとって大きなメリットでした。導入初期にはいくつかの調整が必要でしたが、試行錯誤しながらもスムーズな運用ができました。
After Introduction
データ活用で観光動線を可視化!迅速サポートとシンプルな操作感でスムーズな運営を実現!
導入後の効果
furariを導入して、具体的にどのような効果や変化がありましたか?
参加者の反応やフィードバックで印象的なものがあれば教えてください。
furariを導入し、気候の良い10月と11月に実施したことで、サイクリストを見かける頻度が高くなったと感じました。もともと各市が持つサイクルコースを走っているサイクリストは多くいましたが、イベント期間中は3市のコースを周遊するためか、普段よりも多くのサイクリストを見かけるようになりました。
デジタルスタンプラリーを活用することで、従来の紙のスタンプラリーと違い、スマートフォン一つでチェックポイントを巡れるようになり、参加しやすさが向上しました。参加者からは「普段走っているコースに、こんな場所があるなんて知らなかった」「普段は広島県内を走行しているが、チェックポイントが岡山県にもあったことで、初めて走行してみようと思った」といった声がありました。
イベントがきっかけで新しい発見につながった点は大きな成果です。一方で、サイクリストはあまりお店に立ち寄らない傾向があり、経済効果の面ではどうだったか判断が難しい部分もありました。今後の課題として、地元の店舗と連携し、飲食店や宿泊施設にも立ち寄ってもらう工夫が必要だと考えています。
また、データを確認すると、毎年参加しているリビーターが多いことがわかりました。さらに、どのチェックポイントに最初に訪れる人が多いのか、出発地点の傾向などが把握できるようになり、人の流れを可視化できる点は大きなメリットでした。

サポート体制
サポートを受ける中で、特に助かった点や印象に残った対応はありましたか?
弊社のサポート体制について、感じたことを教えてください。
furariのサポート体制については、全体的に満足しています。特に助かったのは、緊急時など土日でも対応してもらえた点です。イベント期間中は、参加者からの問い合わせが土日に集中することが多く、こちらも対応に追われる中で、運営側が困ったときにすぐに質問できる体制が整っていたのは非常に心強かったです。
また、システムの管理画面がシンプルでわかりやすく、基本的な操作に関して特に困ることはありませんでした。そのため、大きなトラブルもなく、スムーズに運営できたと感じています。一部、スタンプが取得できないといった問い合わせがありましたが、その際も迅速にサポートを受けられたことで、問題をすぐに解決することができました。
特に、位置情報の設定に関する調整など、実際に運用してみないと気づかない部分についても適切に対応してもらえたのは助かりました。全体を通して、furariのサポート体制は充実しており、安心して運営を進めることができました。

今後の展望
今回のデジタルスタンプラリーの導入を、今後どのように活用していきたいとお考えですか?
次回以降、さらに工夫したい点や新たなアイデアがあれば教えてください。
これまで3回実施してきたサイクルラリーでは、3市のコース上にある決められたチェックポイントをすべて回ることで応募できる仕組みでした。しかし、参加者の走行レベルには差があり、上級者にとっては物足りなく、初心者にとっては負担が大きいという課題がありました。
そこで、2025年以降は、チェックポイントの数を増やしつつ、すべてを回らなくても応募できる形に変更したいと考えています。例えば、3市を周遊する条件はそのままに「一定数以上のチェックポイントを巡れば応募可能」とすることで、参加者が自分のペースで楽しめるように調整したいと思います。
また、上級者でも満足できるよう、より広範囲で楽しめるチェックポイントの設定を検討しています。チェックポイントの配置や回り方に自由度を持たせることで、初心者から上級者まで幅広い層が参加しやすい仕組みにしていきたいと考えています。
加えて、furariのシステムを活用して、参加者の動線をより詳しく分析することも視野に入れています。どのルートが人気なのか、どの地点からスタートする人が多いのかといったデータを活かし、より効果的なイベント設計を目指していきます。今後も、サイクリングと地域周遊を組み合わせたイベントを進化させ、より多くの人に楽しんでもらえるように工夫を重ねていきたいと考えています。